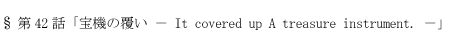
船上のひびきは、物思いから意識を戻して、甲板の中央を振り向いた。太いマストが何本か立つ広い甲板の中央に、低い姿勢をとった奏甲がある。通常のシャルラッハロートに似た、つやのないブルーの外装。だが、それはミリアルデ・ブリッツだった。クアリッタのはからいで、黄金の工房の職人たちが、目立つミリアルデの見かけを変えた結果である。
乗船前、ポザネオ市で初めてこの青いミリアルデを目にしたとき、さすがのひびきも肩を落とした。輝くほどに磨きこまれた純白の装甲に、金細工の紋章やレリーフ、たれ布などで装飾されるような、華燭奏甲としての神々しさは、そこにはなかった。頭部の角もはずされているためか、ミリアルデの顔つきが意外とやさしさものだと、ひびきは感じた。
このミリアルデの変化を説明してくれたのは、工房で待っていたノイエンだった。
過去の歌姫大戦を歌った歌にも、ミリアルデは奮戦した奏甲として『十億の稲妻』と称えられている。誰でもが知っているかもしれないミリアルデをそのままに、旅をすることはできないと。
「工房のみんなが歌ったの。奏甲を構成する幻糸鉄鋼も、幻糸には変わりないから、織り歌で、変わるようにお願いするってわけ。
歌の方は、何人かの歌姫が協力しないといけない、私の知らないムっずかしい歌だけど、色が変わっていく様子は、おもしろかったよ。」
ひびきは奏座に座って起動してみた。操作感覚などは変わっていなかった。それは黄金の工房の歌姫たちによる修理が、確実なものである証拠だ。とはいえ、ソルジェリッタとの調律のもとで、華燭奏甲として戦闘起動するのには、遠く及ばないことも変わらなかった。
ノイエンが言うには、華燭奏甲としてフルパワーで戦闘起動したときには、ミリアルデを構成する幻糸鉄鋼は元の姿を取り戻すらしい。
「絶対奏甲の鋼材は、奏者や歌姫に対応して変化してくんだよ。
幻糸鉄鋼の純度が高い奏甲で、武装なんかに対応して変形や最適化が起こることを<融合装備>とは呼ぶけど、べつに本体だけでも、戦い方や調律によって奏甲は変化するんだから。
だからミリアルデも、華燭奏甲のフルパワーで戦闘起動して、ぴかーって光れば、伝説の『十億の稲妻』に大変身!なんちて、なんちて。
実際は元に戻るって事だけどね。」
工房に運び込む際には、これもやはりクアリッタの手配で、「ケズル」という機奏英雄が、彼の奏甲でミリアルデを運搬してくれたらしい。だが礼を言うにも、彼と彼の歌姫は、すでにクアリッタと共に立ち去っていた。
「クアリッタも忙しいからね。ギネスも梳も、振り回されてるんじゃないかな。」
「ギネスとケズルって、誰?大体、クアリッタって、何者なの?戦いで大変なことになっちゃってるはずなのに、船の手配もできちゃうし、黄金の工房の人たちの面倒みてたり。」
「ギネスと梳は機奏英雄よ。クアリッタは真剣に瑠璃の歌姫として努めてるってところなんじゃないかな。3人ともいろいろ考えてるみたいで、私にはよくわかんない。
梳は、あなたによろしく伝えてくれって言ってたよ。同じ『ニホンジン』だから挨拶したかったそうだけど。知ってる人?」
ひびきは、首を横に振った。梳という名に、元の世界でもアーカイアでも心当たりはない。
修理が終わっていたミリアルデを、船に載せるのは楽だった。歩かせていき、船のバランスが偏らないように、なるべく中央で低い姿勢をとらせる。そうして風を受ける大きな帆の間に、青い奏甲がひざをついて座っていることになったのである。
そしてまもなく、ひびきとノイエンも黄金の工房の人たちと共に、船上の人となったのだった。
青いミリアルデを見上げて、ひびきは思う。ソルジェリッタと仲直りして、2人でミリアルデを全力で起動し、白く輝くハルフェアの旗印、ミリアルデ・ブリッツの本当の姿を取り戻すことがあるのかと。
彼女たちを乗せた船はポザネオ島の北側の内海を西へ進んでいた。遠く南に見える陸地に紫月城を望む位置を通過し、対岸の本島の岸辺へと進路を取る。潮風が、ひびきの自慢のおさげをやさしく揺らしていた。